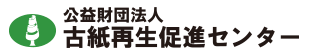Towards 2030 & Beyond
Towards 2030 & Beyondについて
我が国の様々な社会課題解決に向けた布石は2030年までがラストチャンスであり、その影響が未来の可能性を左右するとも言われます。そのような時代にあって、当センターには「環境・経済・社会側面の統合的向上」や「マルチステークホルダーとのパートナーシップ」を念頭に置いた公益事業を通じて、循環型社会形成に関する連携・協働のつなぎ手としての努力が求められています。2024年・センター創立半世紀の節目に、多くの関係者から寄せられた「20」の中長期課題(サステナブルチャレンジ2050)やシンポジウムでの識者助言を受け、2029年度を通過点の節目とした具体的な対策や新たな試みを開始すべく、ロードマップイメージである「Towards 2030 & Beyond」を策定しました。
Towards 2030 & Beyond 取組イメージ
2024
- ・センター創立50周年
- ・半世紀の総括(記念誌)
- ・サステナブルチャレンジ2050
(20の中長期課題提言) - ・内外の中長期需給シミュレーション(第1次、〜2050)
- ・有識者提言ヒアリング
- ・記念シンポジウム開催
2025
- ・Towards 2030 & Beyond策定
- ・第5次循環型社会形成推進基本計面、再資源化事業高度化法
- ・公益法人制度改正法令施行、新制度に向けた対応・点検
- ・新たな公益充実資金項目策定
- ・中長期課題対応強化(新規案件モデル実験開始)
- ・雑がみ需給基礎データ整備
- ・外部パートナーシップ拡大
2026
- ・2025実施の新規取組、モデル実験を踏まえて3ヶ年の強化計画を開始
- ・全原連と連携強化3ケ年計画①
- ・行政と連携強化3ケ年計画①
- ・雑がみ回収・啓発3ケ年計画①
- ・公益法人制度改正法令施行に伴う財務情報開示体制の整備
2027
- ・全原連・創立50周年
- ・全原連と連携強化3ケ年計画②
- ・行政と連携強化 3ケ年計画②
- ・雑がみ回収・啓発3ケ年計画②
- ・国際委員会発足5周年(国際シンポジウム)
- ・紙リサイクルSDGs 制定5周年(公財サステナビリティレポート、ステークホルダー・エンゲージメント、国際イニシアチブ参画)
2028
- ・全原連と連携強化3ケ年計画③
- ・行政と連携強化3ヶ年計画③
- ・雑がみ回収・暋発3ヶ年計画③
- ・紙リサイクルコンテスト20周年(記念・全国拡大イベント)
- ・集団回収顕制度40周年(顕彰対象拡大・新制度)
2029
- ・サステナブルチャレンジ2050 PDCA(第1次)
- ・内外の中長期需給シミュレーション(第2次、~2050)
- ・Towards 2030 & Beyond 総括
- ・センター財政基盤中期見通し (対策案提言)
- ・公益法人制度改正・経過措置完了
- ・公益充実資金執行状況点検
- ・家庭紙委員会発足10周年
2030
- ・第5次循環型社会形成推進基本計画最終年度
- ・脱炭素、SDGs達成の節目
- ・次世代による持続的な紙リサイクル維持に向けたPDCAサイクルの検討
創立50周年記念行事
古紙再生促進センターは2024年3月に創立50周年を迎え、これを記念して創立50周年記念シンポジウム並びに記念誌の発行を行いました。記念シンポジウムでは基調講演並びに5名のパネリストの事例紹介を通じて、紙リサイクルの課題や次の半世紀に向けての提言、センターに期待する取り組みなど様々な意見を頂きました。当日の様子をご紹介します。

紙リサイクルの新たなる挑戦
東海大学副学長、政治経済学部経済学科・教授
慶應大学名誉教授
中部大学理事、学事顧問、名誉教授
細田 衛士 氏
- 「古紙はリサイクルの優等生」と呼ばれるように、日本の紙リサイクルは動脈側と静脈側の間でバランスの取れたシステムである。1997年に古紙価格の下落や逆有償化といった危機に見舞われたが、需給両業界の尽力もあり、紙リサイクルシステムも順調に維持されてきた。しかし、人口減少やデジタル化、紙とプラの複合素材化、雑がみの問題など様々な社会変容に伴う新たな危機が忍び寄っている。
- 社会状況が大きく変容する中、従来の3Rに加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、サービス化等で付加価値を生み出す循環経済(サーキュラーエコノミー)への転換を迎える。これに伴い、リサイクルの優等生である古紙もより循環性の高いビジネスモデルへの転換が迫られる。そのためには動脈産業・静脈産業だけでなく、消費者や投資家を含めた有機的な連携を構築する必要がある。今後は様々なイノベーションやアイデアをもって、資源の高度な循環利用や古紙の高付加価値化を実現し、リサイクル産業から自分たちが高品質な資源を社会に提供しているリソーシング産業へ転換する必要がある。
- 高付加価値の創出のためには、従来の成功体験に固執することなく、モノからコトへの社会変化の波を捉えた新たなるビジネスマインドをもった企業に成長する必要がある。新たなビジネスマインドを持ち、排出者の満足度を高めながら、社会の基礎インフラとして貢献する方向を模索しなければならない。また、紙リサイクルビジネスにおける資源循環インフラとしての役割を果たすためには、高度な資源循環の促進が必要であり、そのためには女性の活躍の場を拡大・発展させ、積極的なイノベーションによって生産性の向上を図る必要がある。収集運搬効率の改善やIT技術導入による効率化等のイノベーションによって、紙リサイクルビジネスを成長させ、人材育成やCSR活動といった事業基盤の底上げにつなげていくビジネスモデルを作り上げていく必要がある。
- 今後、ビジネスリーダーには分析力だけでなく、全体像を直感的に把握する力が必要となる。これらの能力をもって、業界で知恵と知識を共有し、ビジネスマインドを高め、イノベーションの促進によって付加価値生産力を高めることが不可欠である。また、ビジネスを持続可能なものにするため、世代間での円滑なバトンタッチや新たな時代にあった、若く、しなやかな新機軸を率先して取り入れることが必要である。この業界を若い人、女性に魅力のあるビジネスに仕立て上げることが今後の課題である。
- これからの循環経済では、「競争力」に加え、社会課題に対してお互いに連携し、解決に取り組む「共創力」を磨き上げることが重要である。ステークホルダーの連携をもって、前述のビジネスマインドを持ち、新しい資源循環ビジネスを切り開いていくことが求められる。

次なる50年へ
国立研究開発法人国立環境研究所 資源循環社会システム研究室 室長
田崎 智宏 氏
- 課題が複合化する未来が迫る中、未来へのアプローチ手法と人口オーナス(重荷)時代の課題について講演した。
- 変化の時代を乗り越えるアプローチとして、ビジョン創発型政策形成(EnBPM)という手法が挙げられる。これは政策設計者や専門家といった少数のみで問題設計するのではなく、多くのセクターの関係者と協働して問題設計を行い、試行と評価を繰り返しながら政策の実施を進めていくという手法である。古紙を含めた資源循環や持続可能な社会の実現のためには、多くの関係者の連携による将来ビジョンの共創と合意形成が不可欠である。
- 人口オーナス時代を迎え、人口減少や地方の衰退、雑がみの増加、複合素材化といった多くの課題の中で資源循環を維持していくためには、動脈産業・静脈産業だけでなく、消費者も含めた連携が必要である。また、プラスチックや廃棄物等、古紙業界の外側で発生している課題を把握し、他組織との連携をもって協働しながら、課題解決のためのアイデアを創出することが、取組みを有効に進めるために重要である。
- 人口オーナス時代を迎えるにあたって、すでに自治体では雑がみの増加や複合素材への対応といった問題が発生している。自治体がこれらの問題に取り組む際に、どのように働きかけるべきか。
- 自治体ではこの人口オーナス問題について、広域化や施設集約など処理システムを効率化する動きがある。しかし、今までの焼却施設を広域化・集約しても大規模化することは困難であり、いかにスケールダウンしながら現在のインフラを維持していくか、という方向で考えていく必要がある。環境省からも各自治体に資源循環を含めたインフラ維持を考えなさいという通知があったが、現時点で将来像を描けていない自治体が多いことが実情である。この状況でキーワードになるのが「資源の高度化法」という法律で、市町村を超えて広域な視点で事業を考えるきっかけになるため、この新しくできた法律をどのように活かしていくか、という点が今後のポイントとなる。
- 製紙・古紙業界が自治体をはじめとした行政と協働する際のヒントやアドバイスがあるか。
- 現在、各都道府県が広域化・施設集約を考える中で、自治体側も資源リサイクルの実態を把握しきれていない。このような背景の中で、まず相談・議論する場を作ることが重要である。計画策定のタイミングで相談・議論を実施できれば、より良い政策実現につながる。

包装設計から見る「紙化」への期待と課題
包装技術コンサルタント
株式会社パックエール 代表取締役社長
内村 元一 氏
- 様々な容器包装の紙化が進む中で、世界の包装設計の動きと紙化への期待について講演した。
- 世界包装機構(WPO)では「リサイクルのための包装設計ガイドライン」という、世界各国の標準として共有されるガイドラインを公開している。これは、循環型包装設計への世界共通の理解を図るものであり、パッケージの設計段階からリサイクルを考慮することが求められている。また、国内では直近で「プラスチック資源循環法」が施行され、プラスチックの再資源化に資する環境配慮設計が求められている。このように世界・国内問わず資源循環への取り組みとして、設計段階からリサイクルを考慮することが求められている。
- 国内では脱プラ・減プラといったトレンドのもと、様々なパッケージの紙化が進んでいる。このことからプラスチック代替素材としての「紙」への期待は非常に大きいと感じる。一方、現在の紙化は外観の紙化、紙マークの付与が目的となり、実際の材料構成が多様であることから、紙リサイクルにも影響を及ぼしている。今後の循環経済においては、リサイクル可能な紙製包材が求められ、紙化市場拡大には「リサイクルしやすい設計」と「リサイクルスキームの構築」が重要である。
- 世界ではサーキュラーエコノミーにシフトしつつあり、政府も再生材利用の促進に向けた法改正を進めている。包装設計の紙化においても、これまでの脱プラ・減プラを目的とした代替素材としての紙化ではなく、リサイクルしやすい設計や再生材の利用等が求められる方向にシフトしている。この動きを捉え、設計段階からリサイクルしやすい紙製包材の開発・普及を促進する必要がある。この開発・普及は単一企業で実現することは不可能である。幅広い業種の企業を含むサプライチェーン全体での連携と消費者に対する情報公開・啓発活動を通じた消費スタイルの変化の促進が今後の紙化を進めていくうえでの課題である。
- 現在、多くの紙製容器包装が登場しているが、実際に処理する自治体側から見ると様々な特性をもつ容器をどのように処理すればよいのかといった問題が発生している。様々な紙製容器包装の登場に伴う自治体の対処方法について考えを聞かせていただきたい。
- この問題について、企業が消費者や投資家といったステークホルダーに積極的に情報発信することが重要である。その際、単一企業だけで情報発信を行うのではなく、政府やセンターのような様々な団体と連携して進めることが重要である。また、消費者の教育や啓蒙も併せて進めていく必要がある。気候変動や異常気象など身の回りの変化を自分事としてとらえ、消費者の行動が変容していくことが求められる。そのためには、学生だけでなく大人も含めて教育を継続して行う必要がある。

ごみの減量化・資源化に向けて
神奈川県伊勢原市経済環境部
清掃リサイクル課資源循環係 係長
横山 亜紀子 氏
- 伊勢原市で実施した「雑紙救出大作戦」の概要と結果、今後の課題について講演した。
- 伊勢原市では令和4年度から市内小学校を対象に「雑紙救出大作戦」を実施した。この背景として、令和6年に伊勢原市の清掃工場が老朽化のため稼働停止することとなり、燃やすごみの減量につながる取り組みとして始めた。また、新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行によって環境学習の機会が失われた子どもたちへの環境学習の機会として実施した。
- 雑紙救出大作戦は環境教育を行う市内の小学4年生から6年生を対象に、夏休み前に紙類回収袋を配布し、児童自ら家庭で発生する雑紙を集め、夏休み明けに重さを量ってどのぐらいの雑紙が回収できたのか確認してもらうこととした。これによって身の回りにある雑紙という資源を認識し、児童のリサイクル意識の醸成を図ることを目的とした。また、参加した学校には雑紙から再生されたトイレットペーパーを配布し、自分たちが集めた雑紙という資源が新しい製品として戻ってくるという資源循環を実感してもらった。
- 本事業によって、雑紙を知らない・無関心である層に、雑紙分別のきっかけを届けることができた。また、子どもたちを通じて、家庭をはじめとした幅広い年齢層・無関心層に雑紙分別を周知することができた。一方、分別行動を維持、習慣化できるまでの啓発をケアすることができず、行動の維持までつなげることができなかった。今後も環境意識が高い・興味のある方だけを対象とするのではなく、環境に対して無関心な方を巻き込んだ啓発活動を計画・実施することで、誰もが環境意識の高いまちづくりを続けていきたい。
- 人口オーナス時代を迎える中、「雑紙救出大作戦」のような市民の皆様に協力いただく取り組みを維持することは困難であると感じるが、廃棄物処理や分別の維持についてどのような対応を実施しているか。
- これまで市の定めたルールに基づいて市民の自助・共助を前提とした廃棄物処理や分別回収を進めてきたが、高齢化が進むにつれ自身でごみ出しができない方や分別ができずごみを溜め込んでしまう方が増えたように感じる。これらの問題に対して、伊勢原市では高齢者への個別回収を行うごみ出し支援制度を設けて対応している。また、伊勢原市では自治会の加入者が多く、各自治会から代表者に集まっていただき、分別についての議論の場を設け、施策に反映している。人口変動は自治体ごとに違うため、それぞれの自治体にあった施策を進めていくことが重要である。

持続可能な社会づくりのための環境教育の推進
全国小中学校環境教育研究会 会長 東京都多摩市立連光寺小学校 校長
關口 寿也 氏
- 持続可能な社会づくりのための環境教育として、学校現場での知見や考え方について講演した。
- 学校における環境教育の位置づけは、教科・領域の中で取り扱ってほしい教育要素にとどまっている。教科とは国語科、数学科といった教科書のある科目であり、領域とは総合的な学習や特別活動を指す。環境教育の重要性が求められる中、学校教育においては、ICT教育や人権教育、キャリア教育といった複数ある教育要素の一つに過ぎず、学校の状況に応じた取り組みとなり、環境教育に軽重が生まれているのが現状である。
- 気候変動や生物多様性といった環境問題に直面している中で、教員も環境教育の重要性については理解している。しかし、実際に環境教育に取り組むと何を学習させればよいか、どう考えさせればよいか、結論をどうするのかといった様々な課題に直面する。また、環境教育を行ったとしても、環境問題は子どもに手出しできる問題ではなく、学習の成果が活かせないという現実に直面し、消費者教育の限界を感じている。このような経験から、今後は消費者教育の領域を超えて、生産者の立場―例えば政治家や企業の社長など―の教育やアントレプレナーシップ教育(起業家に必要とされる精神や資質・能力の育成を図る教育)が求められている。
- 現在、環境教育の視点を変えて取り組んでいる。これまでは環境問題そのものを学ばせていたが、現在は環境問題を切り口にして、その知識を習得し、対処法を創造するといった教育を実施している。その過程で得た考え方や価値観をもって、将来の変化を予測することが困難な時代に、主体的に問題に取り組む人材を育成することが持続可能な社会を実現するための学習・教育活動である(ESD)。
- ESDを実現するためには外部連携による教育が重要である。外部連携の際には、企業の皆様にはぜひ企業活動の裏も表も話していただきたい。自分の企業の良い側面だけでなく、いま取り組んでいるが上手くいかないことなど、実際に苦戦していることも併せて伝えてほしい。これにより、子どもたちも苦戦しながらも課題に取り組む姿勢や困難でも理想を実現しようとするスピリットといった学校の中だけでは学ぶことのできない考え方や姿勢に触れる貴重な機会となる。
- 人生100年時代を迎える中で、教育の中でも特に大人への教育について、アドバイスはありますか。
- 大人に向けての教育としては、様々な課題や悩みを共有し、皆で一緒に考えていく機会を創出することが重要である。例えば、リサイクルセンターなどで実際にリサイクルに取り組んでいる方にお話を聞き、そこで悩みや課題、実現したい将来像などを共有していただき、そのために自分に何ができるか考えることが必要である。このような共有は子ども・大人や異業種問わず多くの方と進めていくことが、今後の社会づくりにつながる。

日本から学ぶ資源リサイクル:インドネシア人留学生の視点
京都大学大学院地球環境学舎 修士課程2回生
ファティマ シャクラ アズハリ 氏
- インドネシア人留学生という立場から、日本の特徴や資源リサイクルシステムに対する学びについて講演した。
- インドネシアでは古紙をはじめとした資源ごみの回収は政府や行政ではなく、コミュニティにより実施されている。主に家庭で発生したごみを分別回収し、リサイクラーに売却することで得た利益を住民が貯蓄・引き出しできる「ごみ銀行」と呼ばれるシステムで運用されている。このシステムは、インドネシアにおいて家庭から排出されるごみを分別して回収する唯一効果的な制度となっている。しかし、ごみ銀行による資源ごみの回収は、インドネシア全体の資源ごみの1~2%程度にとどまっており、家庭からの分別・回収率を高めることが課題である。
- 日本の特徴として、ポイ捨てや不法投棄が非常に少ないことが挙げられる。古紙のような資源ごみにとってポイ捨てされない環境は非常に重要である。これは常に清掃が行き届いていることやごみ拾い活動によって、街中にごみが散らばっていない状況が維持されているからであり、資源ごみをポイ捨てせず分別して排出するための基盤となっている。また、日本には家庭からの効果的な資源ごみ回収システムが存在する。古紙のような資源ごみにとって、ある一定の出所から資源を回収するというスキームは重要である。日本では自治体の家庭ごみ回収制度がほぼ100%整備されているが、インドネシアでは60%ほどであり、資源回収システムに差がある。他にも家庭ごみの有料指定袋制といった制度もあり、市民のごみ出しに対し、コストをかけることでごみ減量への意識を高めている。このような環境が日本の古紙リサイクルを高い水準で維持している要因と考える。
- 講演の中で、古紙の輸出だけでなく、紙リサイクルの知恵やノウハウを支援してほしいという話があったが、具体的に日本にどのような働きかけを期待しますか。
- 既にJICAなど支援していただいている団体はあるが、政府に対して後押しするような支援を期待している。テクニカルな部分も支援していただければ良い結果となると思う。
- インドネシアには「ごみ銀行」という独自のシステムがあるが、これを実施しているのは公共セクター(政府)でしょうか。
- 実際に現場で実施しているのは地域(コミュニティ)で、コミュニティで集めたごみを提出する先が自治体となる。自治体は集まったごみをリサイクラーに販売し、その利益をごみ銀行に提供するというシステムになっている。
創立50周年記念行事の様子やセンター50年の歩みをまとめた記念誌を発行しました。あわせて、センターが次の半世紀に向けて何を目指すべきなのか、皆様とともに将来を考えるための課題とデータをとりまとめた「サステナブルチャレンジ2050」を発行しました。ぜひご覧ください
創立50周年記念誌はこちら サステナブルチャレンジ2050はこちらまた、Towards 2030 & Beyondに先立ち紙リサイクルへの影響が予想される今後の「社会動向・メガトレンド」をキーワードとしたオンライン・オープンセミナーシリーズ(全6回)を開催しました。あわせてご覧ください。
第1回~第6回オンラインセミナーはこちら